| トップページへ | 「オープンカレッジIN生駒」支援者 | 過去の情報 | これからのオープンカレッジ | 全国情報 | 生駒ポレポレのホームページ |
.gif) |
||
| 学校を卒業したあと、みなさんはどんな毎日を過ごしていますか? 一生懸命働いている人、 お家でお手伝いをしている人、 趣味や楽しみを見つけてがんばっている人 などいろいろだと思います。 そんな毎日の暮らしの中で、 こんなこと知っていたら便利だなと思ったり、 もっといろんなことを知 りたい学びたい と思うことはありませんか? オープンカレッジは障害のある人も、 障害のない人と同じように勉強でき、 学ぶことができ る場です。 オープンカレッジでは大学の先生に来ていただき、 わかりやすく教えていただけます。 |
||
| わが国も含めて世界中の多くの人々が、障害がある故に医療・福祉・教育・雇用。住居など、人として平等であるべき諸権利を剥奪されている。 オープンカレッジ開講の意義は「すべて」の「人」が「人」として生きることが可能な社会の創造であり、障害の有無、年齢、男女、職業、国籍のバリアを超えて、「人」として認め合う人権保障の確立を目指す点にある。 | 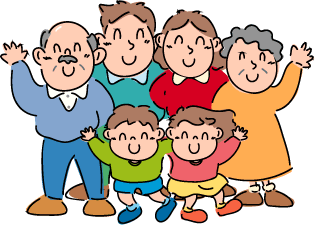 |
|
活動の理念 1、 国際連合やユネスコが提唱する学習権や成人教育・継続教育の保障、つまり、すべての人にある「学ぶ権利」の保障 2、 人間の生涯にわたる「発達・変化」の保障 ――― 知的障害のある人の変化(社会性発達など)を保障 3、 地域における「大学の役割」の変革・創造 ――― 大学の地域への貢献 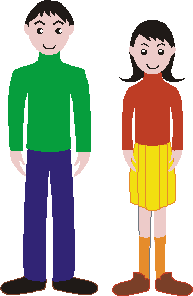 |
オープンカレッジとしての取り組み 1、 知的障害のある人の高等教育を受ける権利を保障するためには、何らかの適切な援助が不可欠と考え、講義内容と方法に考慮し、受講者一人一人に現役学生サポーターを用意した。 2、 受講生が講義を受ける事により得た、よりよく生きるための情報と技術を、自主的に吸収し、仲間と共に、何らかの形でその成果を公表するプロセスを通して、それぞれの自己信頼感をより高め、自己貫徹力を強化する事を期待する。 そのため成就感と臨場体験をより強め課題強制を努めて避けるよう、講師による講義と文化・芸術活動の時間と本人活動の時間を等分に配置した、 3、 生涯学習ニーズのうねりに応じるため、各大学は各種の公開講座や社会人の受け入れなど高等教育機能を地域に提供し始めているが、知的障害のある人々は完全にその埒外に置かれてきた。その知識を、それを求める人に、理解できるように提供する事は、教職にある者の責務である。大学の本来の地域貢献は知的障害のある人をも含めた、すべての市民へのインテリジェンス・テクノロジーの提供によって果たされる。 |
![]()
歴史
 |
1998年 夏 第1回「知的障害のある人のための夏期大学」として、大阪府立大学社会福祉学部安藤忠教授研究室 により開講される。 |
|
以降、武庫川女子大学、桃山学院大学、徳島大学、宮城大学、皇學館大學などで開講の試みが始まる。 また、青森、宮城、奈良など各地に「飛び出せオープンカレッジ」として、講師、大学生が出向いている。 |